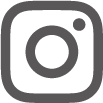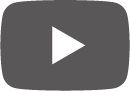Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
テーピングについて知りたい!テーピングの効果や目的を解説 Vol.1
公開日:
執筆・監修者

村木 良博
(有)ケアステーション 代表取締役 スーパーバイザー
(財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー マスター(JSPO-ATマスター)
【役員】
(公財)日本オリンピック委員会 強化スタッフ
(公財)日本テニス協会 ナショナルチーム委員会
(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー部会員
(社団)日本アスレティックトレーニング学会評議員
元日本バスケットボール協会医科学研究部員
元日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部会長
【講師】
花田学園アスレティックトレーナー専攻科非常勤講師
東京有明医療大学 非常勤講師
東京医療福祉専門学校教員養成科 非常勤講師
目次
テーピングとは
テーピングとは解剖学・運動生理学的な身体特性と運動機能の特性を考慮し、粘着性のテープやバンデージ(包帯)などを用いて身体の関節・筋・腱・靭帯を補強、支持することにより、外傷障害の予防・再発防止・応急処置などを目的として行うことを言います。テーピングはもともと、整形外科的な医療の領域で、患部の固定などに使われていましたが、スポーツによるケガ、とくに足関節の捻挫の予防や悪化防止に効果があることで、スポーツに幅広く使用され、今日に至っています。
その間さまざまな技法や素材を使ったテーピング技法があふれていますが、テーピング本来の目的である関節可動域の制限する「スポーツテーピング」について紹介します。

テーピングの目的
テーピングの目的には、1)外傷障害の予防、2)外傷障害の再発防止、3)応急処置などがあり、その目的に合わせた巻き方やテープの素材、サイズなどが選択されます。【テーピングの目的】
1)外傷障害の予防
2)外傷障害の再発防止
3)応急処置
外傷障害の予防
特定されたケガの発生が予見できる頻度の高い部位や外傷を未然に防ぐ目的で使用されます。スポーツで発生するケガの多くは下肢、特に足関節で起きており、その大半が足関節の捻挫(靭帯損傷)だと言われています。
この足関節捻挫の大半は、足関節の外側の靭帯を痛める「内反捻挫」(つま先が下がり、足の裏が内側を向くことによる足関節の外側側副靭帯の損傷)で発生しています。

*図2:内反捻挫
特定されたケガの発生が予見できる頻度の高い部位や外傷を未然に防ぐ目的で使用されます。
スポーツで発生するケガの多くは下肢、特に足関節で起きており、その大半が足関節の捻挫(靭帯損傷)だと言われています。
この足関節捻挫の大半は、足関節の外側の靭帯を痛める「内反捻挫」(つま先が下がり、足の裏が内側を向くことによる足関節の外側側副靭帯の損傷)で発生しています。

ATHMD スリーブタイプ 足首用 日本製 (1枚入)
外傷・障害の再発防止
最も多く使用されている用途は、外傷・障害の再発防止を目的としたもので、ケガをした部位の再受傷を低減させるために、運動が禁止されていない回復途中の部位や、ケガの後遺症による不安定感を低減させる目的で巻くことです。現在、ケガをしている人や以前ケガをしたことのある人は、同じ部位を再び同様のケガをしないようにすることを目的としてテーピングを行います。
また、リハビリテーション期間中でも再発する恐れや、痛みを軽減する目的からテーピングをしてリハビリテーションをすることも行われます。
関節や筋肉を安定させることで、不安感を取り除くことにもなり、精神的な支えとなることもあります。
応急処置
応急処置の場面でテーピングが用いられることもありますが、あくまでも良肢位(りょうしい:正しい位置)で固定し、安静にさせる事が目的のため、この目的でテーピングして運動に復帰することはありません。しかしながら、現在では応急処置の方法や機能性の高い固定装具などがでており、応急処置を目的としたテーピングの頻度は高くありません。
むしろ正しい応急処置法を迅速に的確に行う方が、その後の経過に影響を及ぼすことが少なくなります。
応急処置のRICE処置については、こちらをご覧ください。

テーピングの効果
テーピングの効果として、1)、2)靭帯、腱の補強(靭帯や腱の走行に合わせ、関節可動域を制限する)、3)局所の圧迫(筋肉など任意の限局された部分に圧迫をかける)、4)痛みの緩和(関節を安定させることで痛みを緩和させる)、5)精神的な支え(ケガへの不安感が減少する)などの効果を期待できます。【テーピングの効果】
1)関節可動域の制限
2)靭帯、腱の補強
3)局所の圧迫
4)痛みの緩和
5)精神的な支え
テーピング時の注意点
テーピングする際の注意点がいくつかあります。 これは、テーピングの効果を高め、できる限り長く保ち、テープを巻くことによる二次的な弊害を防止するために必要です。テーピングの効果は、身体に密着し、動いてもずれが少ないことです。
また、テーピングをする目的を明確にすることにより、テーピングの技法が決まるため、予防なのか、ケガの保護なのか、目的をはっきりさせることが最も大切です。
一番重要な点は、テーピングの目的を明確にすること。予防なのか?ケガの保護なのか?を明確にし、ケガの場合はまずその病態を的確に把握することです。それによってテープの種類やサイズ、巻き方が決められます。

*図4 :テーピングをする部分は清潔に
「テーピング前の注意点」
1)テープを貼る部位は清潔にする
2)擦り傷、切り傷の保護
3)体毛を剃る
4)粘着力の強化
5)皮膚の保護
6)摩擦部位の保護
7)部位にあったテープの選択
テーピング中の注意点とテープを外した後の処置
テーピングを始めたら、次のことに注意しましょう。 皮膚とテープの間に隙間が多くなると、擦れや、かぶれなどが生じることがあるため皮膚全体にテープ面が密着するように、しわやたるみがないようにしましょう。これらがあると皮膚への圧迫が局所にかかり、擦れや、かぶれの原因となりますので、テープは常にピンと張った状態を保ち、テープ全体が皮膚に密着するように巻いていきます。
テープとテープにすき間があると、これも皮膚に悪影響を及ぼすため、動いている間にすき間ができないようにテープとテープの重ね合わせを1/2以上重ねて巻きます。こうすることで、動きによるすき間の発生を防ぎます。
テープを巻くときの力の入れ方にも注意が必要で、皮膚が盛り上がるほどきつく巻いてしまうと、血行障害を引き起こすことがあります。 「テーピング中の注意点」
1)テープは、たるみ、すき間、しわなど極力少なくする
2)テープの張力は一定にする
3)テープとテープの重ね合わせは1/2以上重ねる
4)血液の循環障害の有無を確認する
また、テーピングは運動時に関節や筋・腱を守ることに使用するため、運動が終わったらできるだけ早く取り除きましょう。
長い時間テープを巻いたままの状態は皮膚にダメージを残すため、テープを外したら皮膚に残っている粘着物を取り除き、保湿クリームなどで皮膚の保護に努めてください。かぶれなどの皮膚の問題が少なくなります。

*図5 :テープを外した後のケア
【運動後、テープを外した後の処置】
1)運動後はすぐにテープを外す
2)皮膚についた粘着物をふき取る
3)皮膚の保護(保湿クリームなど)
テーピングの目的で、応急処置としてのテーピングとありましたが、その主な目的としては固定と圧迫で良肢位(正しい関節の位置)に固定し、安静状態を保つためにあり、この目的でテーピングを施しスポーツに復帰することは少なくなりました。
ではケガをしたらどのような方法で処置をしたらよいのでしょうか?
R.I.C.E処置
スポーツでは、ケガをした直後に行う応急処置として「R.I.C.E処置」が普及しています。※ボディケアブログの最初のコンテンツ「ケガの原因と対処法」にも書いていますので、併せてご覧ください。
ケガが起きたときに、からだの中の組織が損傷されます。
損傷には大きなものや小さいものがありますが、いずれの場合にも急性期の症状が現れます。
それは、痛み、充血、腫れ(赤みを帯び腫れあがる)、熱感、普通に動かすことができない、などの症状です。
これを最小限に止めて、ケガの回復期間を短縮することができます。
R.I.C.Eとは、応急処置で行う行為の頭文字をとっています。
R:Rest 安静
ケガの悪化を防ぐために、患部を安静に保ち、むやみに動かないように安静を保ちましょう。I:Ice 冷却
患部を氷や冷水を用い冷却することで、冷却材は氷が一番安価で効果的です。氷をビニール袋または氷嚢へ入れて、水を少し含ませます(凍傷を防ぎます)。
注意:保冷材は氷結したものをそのまま皮膚の上に充てると、凍傷を起こす危険が高いため、ビニール袋に水と一緒に入れ、さらに患部には水で濡らしたタオルを充てその上から、直接保冷剤が皮膚にあたらないようにして冷却しましょう。
C:Compression 圧迫
患部を弾性の包帯などで圧迫を加え、過剰な腫れや痛みを軽減することに役立ちます。E:Elevation 挙上
患部の循環を制限するため心臓より高い位置に挙げることで、痛みや腫れなどを抑える効果が期待できます。この一連の行動を1回につき、冷たいという感覚がなくなるまで(冷却時間は個人差があるため、感覚で調整)継続し、いったん氷を外しますが、圧迫と挙上は継続します。
局所の熱感や痛みを再び感じたら再度RICE処置を行います。
これを24時間から72時間程度(初期の炎症症状である熱感、腫れ、痛みなどがある程度納まるまで)継続します。

*図6:RICE処置
もちろん体のなかで何が起きているかを確かめる必要がありますので、医療機関での診察を受けるようにしましょう。
Invalid password
Enter
アイテムから選ぶ
競技から選ぶ

Copyright © D&M Co.,Ltd. All Rights Reserved.
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします