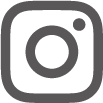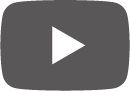腰痛を予防するには?腰痛に効くストレッチを紹介 vol.2
公開日:
執筆・監修者

村木 良博
(有)ケアステーション 代表取締役 スーパーバイザー
(財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー マスター(JSPO-ATマスター)
【役員】
(公財)日本オリンピック委員会 強化スタッフ
(公財)日本テニス協会 ナショナルチーム委員会
(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー部会員
(社団)日本アスレティックトレーニング学会評議員
元日本バスケットボール協会医科学研究部員
元日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部会長
【講師】
花田学園アスレティックトレーナー専攻科非常勤講師
東京有明医療大学 非常勤講師
東京医療福祉専門学校教員養成科 非常勤講師
目次
イスに座ったままできるストレッチ
イスに座っての仕事ができるようになると、同じ姿勢を長く保つことで臀部、腰部、ハムの筋肉が固まり、動き出す際に腰に痛みが出ることがあります。それらを防ぐために、時々筋肉をストレッチしましょう。
その時はイスに座ったままできるストレッチがお勧めです。
⑧イスに座ってのヒップストレッチ
椅子に腰かけた状態で、片足をもう片方の膝付近に乗せ、スネや膝の方向に身体を倒していきましょう。
この時も顔は前、顎を床につけるように背中を伸ばして、臀部の筋肉が延ばされていることを感じましょう。

*図12 ⑧イスに座ってのヒップストレッチ
⑨イスに座っての下腿とハムのストレッチ
下腿とハムは、椅子に少し浅く座り、片脚を前に伸ばし、つま先を上げることで下腿後面の筋肉がストレッチされ、さらに前かがみになることでハムをストレッチすることができます。
背中が丸まらないように、顔は前を向き顎をつま先につけるようにストレッチします。

*図13 ⑨イスに座っての下腿とハムのストレッチ
⑩イスに座ってのツィスト
椅子に腰かけたまま上体を左右に捻り、腰背部の筋肉を伸ばします。顔は捻る方向へむけ身体を搾るようにしてストレッチします。

*図14 ⑩イスに座ってのツィスト
腰痛を防止するエクササイズ
痛みもなく、少し動けるようになったら、ストレッチの方法も関節を大きく伸ばす方法に代え、さらに硬くこわばった筋肉を積極的に動かして動きに慣らしていきましょう。日常の動作で支障がなくなっても再発を防止するために、体操やウォーキング、スクワット、階段上り(下りは膝に負担がかかるため昇るだけ)など、お尻や太ももの筋肉を鍛え、自分の身体を支えられる筋力を保つように心がけましょう。
①ドローイン
ドローインは、腹圧を高めるため体幹部のインナーマッスルを鍛える方法で、腰痛の解消に欠かせないエクササイズです。
腹圧を高め体幹の筋肉を鍛えることで、腰椎の過度な前弯(反り腰)を改善することが期待され腰痛の予防効果が高まります。
ドローインのイメージは、風船を膨らませるように息を細く吐きながらお腹の周りを包んでいる筋肉を収縮させていきます。
その際に、お腹をへこませ、腰の後ろ部分が床に密着するようにすると効果的です。

*図15 ①ドローイン

*図16 ドローインの腹圧を高めるイメージ
②トランクカール・ヒップリフト
腹筋とヒップの筋肉を積極的に動かします。仰向けで床に寝て両膝を立て、両手をモモの前にあてます。
①ドローインの要領で息を吐きながら、頭、背中、腰を順に丸めるように体を起こしていきます。
実際に体を起こし切らなくて構いません。できるところまで丸めたら2-5秒止め、その後ゆっくりと戻ります。
次に、腰を床からゆっくりと挙げます。
お尻に力を入れてモモと体が一直線になるところで止めましょう。腰が反らないように気を付けましょう。2-5秒止めた後、ゆっくりと床に戻します。
この動作を5~10回ほど繰り返します。

*図17 ②トランクカール・ヒップリフト
③スクワット
膝と股関節を曲げ、立ち上がる動作で、自身の体を足の力で押し上げる力を養います。
階段昇り、登り坂の動作を強化するのに役立ちます。
両脚を肩幅に開き、つま先は前またはやや外側に向け立ちましょう。
手は頭の後ろまたは胸の前で組みます(腕を前に挙げておく姿勢でも構いません。自身のやりやすい姿勢を見つけましょう)。
足首、膝、股関節をゆっくり曲げていきます。
慣れない方は、椅子の背に両手を乗せ、身体を支えながら行ってください。
曲げる膝の向きは、つま先と同じ方向にします。この時、膝がつま先より前に出ないこと。
(後ろの椅子に腰かけるイメージでおこなう)
背中が丸まって、身体が前に倒れないこと。
(顔を少し上に向け、目線はやや上を見るようにすると背中の丸まりなどが防げます。)
足首が硬く、うまくしゃがみ込みができない方は、5㎝ほどの高さになる板などにかかとを乗せ高くすると、しゃがみ込みがしやすくなります。
膝を曲げる角度は、最初は30度くらいで、目標は90度まで曲げてこらえられるようにしたいです。
しゃがみ込む時は、息を吐きながらお腹に力を入れて体幹を安定させてからしゃがみ込みを始めます。
1度に5~10回。これを2~3セット繰り返します。

*図18-1 ③スクワット(手を頭の後ろ)

*図18-2 スクワット(手を前に挙げる)
④ステップアップ(階段昇り)
階段昇りは、スクワットと同じく身体を上へ押し上げる、臀部やモモの筋肉を鍛えるのに有効です。
駆け上がるのではなく、一歩一歩ゆっくりと昇ることで筋肉が鍛えられます。
筋肉が鍛えられるのは、昇りが有効ですが階段の下り、下り坂は筋肉の使われ方が違い、膝に大きな負担がかかるため、膝を痛めている方は昇りだけにするといいでしょう。

*図19 ④ステップアップ(階段昇り)
まとめ
一度つらい腰痛を経験すると、もう二度と同じ苦痛は避けたいものです。
腰痛の多い季節として春から夏へ(4月~6月)、夏から秋へ(9月~11月)季節の変わり目には、温かい日と、寒い日が交互になる期間が続くと、寒暖の差に身体が順応しきれない状態でそれらが繰り返されると、身体には大きな疲労となって蓄積し、そこへ不安定な動作が加わることで腰痛を引き起こしてしまします。
普段の生活での姿勢やしぐさに気を付け、セルフケアで腰痛防止に努めましょう。
ぎっくり腰などの急性腰痛はこの季節の変わり目に非常に多く発生していますので、普段の生活などに気を付けるなどセルフケアが重要な季節となります。
このような時期には、日中の温かさで汗をかき、朝晩の冷え込みで身体が冷えるということを繰り返すことでその変化に順応することが追い付かずに疲労が蓄積し、身体や筋肉が硬く冷えた状態になりやすくなります。また長時間同じ姿勢を続けることでも腰や臀部、背部の筋が硬くなる傾向にあります。
長時間の同一姿勢には、就寝、デスクワーク、長距離の自動車運転、立ち仕事などがあり、同じ姿勢を続けたあとに行う動作(負荷)が引き金となって腰痛を起こすことがありますので、同じ姿勢を続けた際には急に動き出すことなく、少し体を動かして(ストレッチや軽い体操など)から動き出すと腰痛の防止に効果的です。
次回予告
腰痛を予防する普段の生活で気を付けるべきこととは?姿勢やセルフケアをご紹介
アイテムから選ぶ
競技から選ぶ

Copyright © D&M Co.,Ltd. All Rights Reserved.