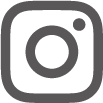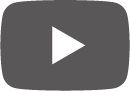Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
筋肉痛はなぜ起こる?効率的なトレーニング方法と適する食事を含めた計画 Vol.2
公開日:
Vol.1では、筋肉痛が起きる原因と対処法、また、その際に症状による注意点などを解説していきました。
今回は、トレーニングの原理と原則に沿って効果的な筋トレ方法と、食事を含めたトレーニング計画について解説していきます。
執筆・監修者

村木 良博
(有)ケアステーション 代表取締役 スーパーバイザー
(財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー マスター(JSPO-ATマスター)
【役員】
(公財)日本オリンピック委員会 強化スタッフ
(公財)日本テニス協会 ナショナルチーム委員会
(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー部会員
(社団)日本アスレティックトレーニング学会評議員
元日本バスケットボール協会医科学研究部員
元日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部会長
【講師】
花田学園アスレティックトレーナー専攻科非常勤講師
東京有明医療大学 非常勤講師
東京医療福祉専門学校教員養成科 非常勤講師
目次
効率的な筋トレとは?
筋トレは、毎日すれば効果が出るとは限りません。まず筋トレを効率的に進めるためには、トレーニングをする目的を設定することから始まります。
どのような体になりたいのか?
その体力をどのように使っていくのか?
その目的によって負荷(重量)、数(回数とセット数)、頻度などを加味しプログラミングしていきます。
つまり闇雲に思いつきでするものではなく、計画的に行うことで効率よく効果を上げていくことが大切です。
トレーニングには「筋力トレーニング」 「代謝系トレーニング」 「コーディネーショントレーニング」 「スタビリティートレーニング」 「アジリティトレーニング」など様々な方法があり、その人の目的に沿ってこれらを織り交ぜプログラミングし、それを実行することで効果が出てきます。

筋力トレーニング(レジスタンストレーニング)
筋トレ(筋力トレーニング)は、筋肉に負荷をかけて行うことから「レジスタンストレーニング(抵抗トレーニング)」と呼ばれています。つまり筋肉に抵抗(負荷)をかけて、「大きく・強く」していくトレーニング法です。
筋トレは、各部分の筋肉に負荷をかけて、筋を肥大させていくことが最大の目的と思います。
ボディービルダーのように筋肉一つ一つを「大きく・きれい」に鍛えてその美を競うものですが、それ以外に目的(例えばスポーツに必要な筋力)を達成するための一つの筋力的な土台を作り、その上に専門的な体力要素のトレーニング(代謝系トレーニング、コーディネーショントレーニング、スタビリティートレーニング、アジリティトレーニングなど)を積み上げ、スポーツパフォーマンスを上げていくことを目的としていることもあります。

トレーニングの原理と原則
筋トレは、一つ一つの筋肉を鍛えていくために長い時間と努力が必要になり、それらを効率に進めていくため、いくつか基本的に知っておかなければならないことがあります。トレーニングには、3つの原理(3大原理)と5つの原理(5大原則)があり、これらはトレーニングの効果を示す法則のようなものです。

トレーニングの3大原理とは
1.過負荷(オーバーロード)の原理2.特異性の原理
3.可逆性の原理
1.過負荷(オーバーロード)の原理
身体、筋肉に一定の運動負荷を加えることで、その機能が向上するということです。いつまでも同じ負荷を加えていても、それ以上の効果は出なく、徐々に負荷を増やしてトレーニング(オーバーロード)することによって効果が上がっていくということ。
2.特異性の原理
トレーニングはその方法などによって効果が変わり、トレーニングを行う部分には、その効果が現れるということです。腕のトレーニングをしたら腕の筋力が、脚のトレーニングをしたら脚の筋力が向上します。継続的に走ることで持久力が向上します。
3.可逆性の原理
一度トレーニングで筋力を高め、それをやめてしまうと筋力は元の状態に戻ってしまいます。したがって、継続的に行うことが必要だということです。
トレーニングの5大原則とは
1.全面性の原則2.個別性の原則
3.意識性の原則
4.漸進性(ぜんしんせい)の原則
5.反復性の原則
1.全面性の原則
トレーニングは、個々の筋肉だけではなく、全身をバランスよく鍛えることが大事です。代謝系(有酸素運動、無酸素運動)、コーディネーショントレーニング 、スタビリティートレーニング 、アジリティトレーニング、柔軟性などの体力要素もバランスよく全身的に高めることで効果があります。
偏ったトレーニングはトレーニング効率を下げるばかりか、身体のバランスが崩れその結果ケガや体調不良などの原因にもなるため全身的にトレーニングしましょう。
2.個別性の原則
その人が持つ特徴、能力に合わせたトレーニングが必要です。年齢、性別、体力、生活環境、習慣、性格、スポーツなど自分の目標や目的に合わせたトレーニング法は効率的に実施でき、それを継続できる意欲にもつながります。
3.意識性の原則
トレーニングを実施する際には、目的意識をもって行うことが大切です。トレーニングの目的や内容、意義をよく理解し、積極的に取り組むことと、このトレーニングでどこが鍛えられ、何が得られるのかを意識することでトレーニング効果が向上します。
4.漸進性(ぜんしんせい)の原則
トレーニングは、それを積み重ねることによって効果が現れます。トレーニング負荷の強度やそれにかける時間、頻度など、段階的にプログラムすることが大切です。
トレーニングをすればすぐに筋力が付くわけではありません。
少しずつ手順を踏まえ、段階的に行うことで、効果が上がり、またそれを持続させていくことで得た効果が落ちにくくなります。
5.反復性の原則
トレーニングは継続的に反復することでより大きな効果が得られます。トレーニング効果を出すには、数回行っただけでは効果は期待できなく、最低限週3回(日)以上、規則的に継続して行うことが重要です。
トレーニングの計画
また、筋トレはやればやるほど効果の上がるものではありません。原理、原則を踏まえ、トレーニングの頻度(1回、1日、1週間あたりに実施する回数)や運動強度、それにかける時間などの調整が必要です。
同じことを毎日やるのと3日に1回やることを比べると効果的には同じと言われていますので、効率を考えれば3日に1回のトレーニング頻度でも効果があることになります。
ただ体の各部分を鍛えることになりますので、当然種目が多くなり1回にかかる時間が多くなります。そこで計画が必要になります。
例えば、1回のトレーニングを3回に分けると時間は1/3となりますが、その際トレーニングする部位を、1日目は、上半身、2日目は下半身、3日目は体幹など部位を分ける方法が考えらえます。
また、重いウエイトで行うトレーニング、軽いトレーニング、走るなどの代謝系、素早さを鍛えるアジリティ系などのトレーニングを織り交ぜたプログラムにすると、毎日種目が変わって気分的にも切り替えができて効率よく進められるようになります。

休養と栄養補給はとても重要
トレーニングばかりでは、効率よく体は鍛えられません。トレーニングで負荷をかけ続けると筋は疲労し、それに耐えられるよう身体は作り代えられます。
その際に、妨げとなるのが筋のコンディション(状態)です。
硬いこわばった筋肉は、その作り代えの作業を妨げ、さらに筋を鍛える土台がもろく崩れる状態では、そこに積み上げることができません。
トレーニングを積み上げるには、筋が柔軟性と弾力性をもち、栄養たっぷりであることが作り代え作業の前提となります。
 したがってトレーニングをした後は、柔軟性や弾力性のある良い状態に戻してあげなければなりません。これを超回復といいます。
したがってトレーニングをした後は、柔軟性や弾力性のある良い状態に戻してあげなければなりません。これを超回復といいます。さらに、筋肉はタンパク質で構成されていますので、食事でタンパク質を補給しないと、筋肉の作り代えができません。
さらにタンパク質だけでなく、筋の機能に必要な他の栄養素もバランスよく補給する必要があります。
5大栄養素と効果
1.蛋白質:からだをつくる主成分2.糖 質:エネルギー源
3.脂 質:エネルギー源、細胞膜の構成成分
4.ビタミン:からだの機能を整える
5.ミネラル:からだの機能を整える

まとめ
トレーニングは、徐々に負荷を増やし、継続的に行うことで効果が出ます。
筋肉の状態が悪い(疲れている、硬い、痛みがある)場合には、その効果が反映されないばかりか、逆効果となることがあります。
計画的、継続的に行いましょう。
トレーニング後には、休息を入れ、筋の疲れを取り除き、食事で栄養を補給し筋や身体が十分整った状態に戻ってからトレーニングを積み上げていかないと効果は期待できません。
安全で効果的なトレーニングを心がけてください。
次回予告
日本の成人の90%が、なんらかの機会に経験しているという「腰痛」に関して解説していきましょう。
Invalid password
Enter
アイテムから選ぶ
競技から選ぶ

Copyright © D&M Co.,Ltd. All Rights Reserved.
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします