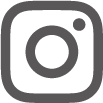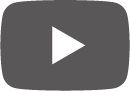Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
肩が痛い!肩の痛みは四十肩・五十肩だけでない。痛みの原因と予防とは? Vol.1
公開日:
肩の痛みにはさまざまなものがあります。
肩の痛みは主に肩関節周囲に起きる痛みや動作痛で、肩こりの肩(肩関節と首の付け根の間、肩甲骨の上の部分)とは部位が異なります。
※肩こりについては「肩こりを解消しよう!肩こりが起きる原因と対策」をご参照ください。

執筆・監修者

村木 良博
(有)ケアステーション 代表取締役 スーパーバイザー
(財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー マスター(JSPO-ATマスター)
【役員】
(公財)日本オリンピック委員会 強化スタッフ
(公財)日本テニス協会 ナショナルチーム委員会
(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー部会員
(社団)日本アスレティックトレーニング学会評議員
元日本バスケットボール協会医科学研究部員
元日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部会長
【講師】
花田学園アスレティックトレーナー専攻科非常勤講師
東京有明医療大学 非常勤講師
東京医療福祉専門学校教員養成科 非常勤講師
目次
肩の痛み「肩の構造」
「肩関節(かたかんせつ)は、上腕骨(じょうわんこつ)と肩甲骨(けんこうこつ)のつなぎ部分を指しますが、上腕骨の関節頭(かんせつとう)に比べ、関節窩(かんせつか:関節の受け皿部分)が小さいため、他のどの関節よりも動く範囲が大きい関節です。したがって肩関節の上には肩甲棘(けんこうきょく)と鎖骨(さこつ)の関節が、屋根のように覆っている肩峰(けんぽう)があり、ここを第2肩関節と呼ばれ、機能的に肩関節を安定化させています。(ほかにも機能的に作用する部分があります)

※図 肩の骨格
肩関節には、肩甲骨から上腕骨頭にかけて、肩の回旋動作に深くかかわる棘上筋(きょくじょうきん)、棘下筋(きょっかきん)、小円筋(しょうえんきん)、肩甲下筋(けんこうかきん)が付いており、「肩回旋筋(かたかいせんきん):ローテーター」と呼ばれています。
この4つの筋肉が上腕骨頭の周りに一つの平たい腱となって付いており、これを「腱板(けんばん)」といいます。
さらに肩関節の周りには比較的大きな三角筋(さんかくきん)、広背筋(こうはいきん)、僧帽筋(そうぼうきん)などで覆われ、肩関節の大きな力強い動きを作っています。
肩関節の痛みはこうした肩関節を構成する、関節自体や関節包、筋、腱、腱板などに損傷を伴うことで起きます。

図 肩周囲の筋肉
急性と慢性の代表的な肩のケガ
急性の外傷(ケガ)では、骨折、脱臼、捻挫、筋腱の損傷など、急激なひねりや打撲などによって引き起こされます。代表的なものに肩関節の脱臼、肩鎖関節(けんさかんせつ)の捻挫や脱臼、鎖骨骨折などがあります。
一方、慢性の肩障害は、繰り返しの動作で肩関節または肩周囲の筋群に摩擦や悪い動作の繰り返し、疲労の蓄積などによって筋腱に障害が引き起こされるケガをいいます。
代表的なものに、上腕二頭筋長頭腱炎(じょうわんにとうきんちょうとうけんえん)、投球動作によりおきる投球障害肩(とうきゅうしょうがいかた)があげられます。
腱板損傷(けんばんそんしょう)は、急性でも慢性でも起きることがあります。
加齢による四十肩、五十肩は、原因が定かではありませんが、一度発症すると腕が上がらないなどつらい症状が長期に渡って続くことがあります。
肩のケガ① 肩関節脱臼(かたかんせつだっきゅう)
肩関節が不安定な動作(外転+外旋位)を強制されることや、転んで手を地面に着いた際に肩にひねりが加わると、肩の関節は簡単に外れてしまいます。これは肩関節の可動域が非常に大きく、不安定な関節であることからわずかな外力でも起きてしまうことがあります。
脱臼や骨折では医療機関で外れた関節を元に戻し(整復)、外れた際に傷んだ靭帯や筋腱、関節包が修復するまで長い期間固定をしなければなりません。
通常は3週間、スポーツ選手ではしっかり安定するまで4週間固定することが一般的ですが、何度も脱臼を繰り返している方(習慣性肩関節脱臼)は、関節面に肩が外れる際にできた道スジができていることが多く、再発を繰り返すため、手術が必要なケースも見られます。
初回の受傷であれば、しっかりと固定をしましょう。

※図 肩関節脱臼

※図 固定
肩のケガ② 腱板損傷(けんばんそんしょう)
腱板損傷は直接、関節の急激なひねりや外力を受けて引き起こされることもありますが、繰り返し外力を受け負荷が蓄積した結果、腱板の擦れが大きくなり、腱板が損傷されることもあれば、加齢による筋腱の衰えによっても起きることがありますが、四十肩、五十肩とは分けて考えます。また、悪い動作の繰り返しによって肩関節の上に屋根のようになっている肩峰(鎖骨外端と肩甲棘のつなぎ目)と上腕骨の間に腱板が挟まって腱板を損傷してしまう「インピンジメント症候群(投球障害肩)」は、腕を挙げる動作をするスポーツ(野球、テニス、バドミントンなど)に多く見られます。
 ※図 投球動作(野球)
※図 投球動作(野球) ※図 投球動作(テニスサーブ)
※図 投球動作(テニスサーブ)若年層では、無理な投球を繰り返すことで腱板が引っ張られ上腕骨の成長線部分に障害が起きるリトルリーガーズショルダーなどがあるため、成人との若年層ではケガの違いを考慮しなければなりません。
インナーマッスルとアウターマッスル
肩の回旋筋は、身体の深いところにあり比較的小さな筋群で「インナーマッスル」と呼ばれています。それを覆うように比較的大きな筋肉(三角筋、広背筋、大小胸筋、僧帽筋など)が表層についています。インナーマッスルは、初動(動作のはじめ)に関節などを安定させる働きがあり、まずここが安定しないと動作に不具合が出てきます。

※図 インナーマッスルとアウターマッスル
肩の回旋筋は、肩甲骨から棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つの筋肉が上腕骨に一枚の板のようになって強固に付着しており、外見上、袖口の形に似ていることから、「ローテーターカフ」(回旋筋の袖口)という俗称が付いています。また、回旋筋を「カフマッスル」と表現していることもあります

※図 ローテーターカフ(回旋筋の付着部)
腱板損傷はこのカフの部分、とくに棘上筋、棘下筋の腱板付着部に多く発生しています。これは、ちょうど肩峰の屋根の下にあるため、不正な動作を繰り返すと、肩峰と腱板が挟まれ(インピンジ)、それがさらに擦れると、腱板損傷に発展します。

※図 インピンジメント症候群
肩の回旋筋を含むインナーマッスルのエクササイズでは、強度の高いチューブやバンドで、グイグイ行うとインナーマッスルが動く前に、外側の大きな筋が優位に動き出します。
そのため、安定化されないまま関節が動くことになり、不正な動作につながります。
インナーを動かすためには、比較的強度の低いチューブやバンドを使って、鍛えるというより正しく動かすことにポイントを置きましょう。最初のうちは何も使わずにただ動かすだけでもいいと思います。正しい動作ができたらごく軽い抵抗をかけ徐々に負荷を上げていくことが重要です。フォームが崩れないように鏡を見て確認しながら行うこともおすすめです。
これがしっかりできるようになれば、アウターマッスルを含めた強度の高いエクササイズに移行し、総合的な動きや強度を上げていくことが必要です。
肩のケガ③ 四十肩、五十肩
四十肩、五十肩は、加齢による筋腱の弱化と肩にかかる負荷の蓄積により肩が挙がらない、手を後ろに引けないなどさまざまな動作に支障をきたすことがあります。四十肩、五十肩は病名ではありません。
肩関節周に炎症が起こり、肩周囲の筋腱、関節自体が硬くなり、関節内で癒着(ゆちゃく)するなど、腕を挙げられないくらいになる症状でとくに40~50歳代によくみられることから、このような俗称が付いています。
この年齢層では、腱板自体のみずみずしさが失われ、腕の重みや腕を良く使う動作やスポーツによって腱板などの肩の筋腱、関節包などに炎症や拘縮を引き起こすことが考えられます。
専門医でレントゲン検査、MRI検査、エコー検査などで主だった組織の損傷があれば、それが原因となりますが、多くの場合は臨床所見がなく正直なところ原因は明らかではありません。

次回予告
この章では肩のケガについて詳しくまとめていきました。
次回、肩のケガの予防や回復など、自宅で簡単にできる解決策について詳しく解説していきます。
Invalid password
Enter
アイテムから選ぶ
競技から選ぶ

Copyright © D&M Co.,Ltd. All Rights Reserved.
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします